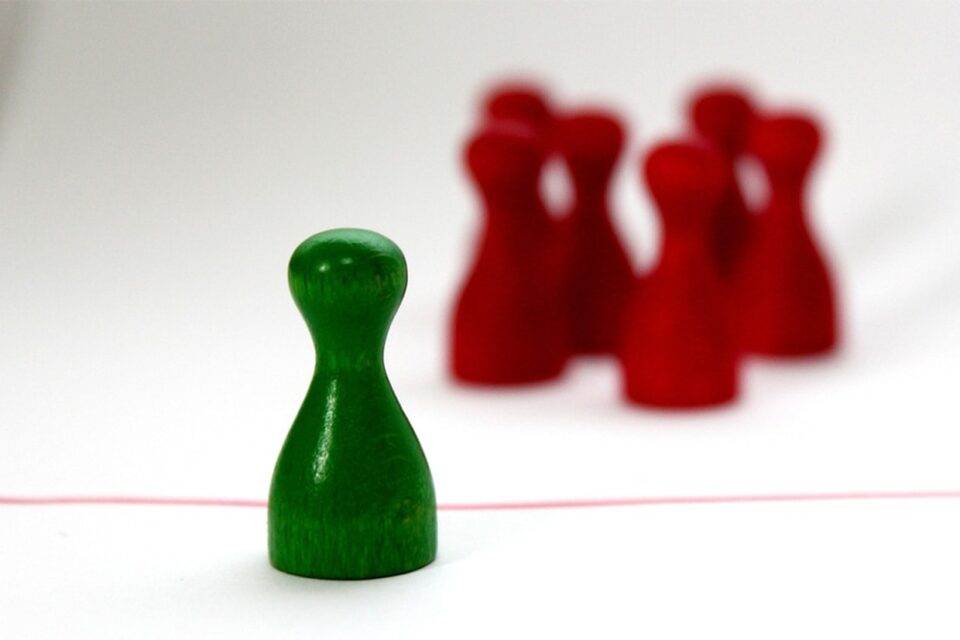企業のバックオフィスを支える「事務職」と「経理職」は、どちらも日常業務の円滑な運営に欠かせない存在です。しかし、両者の違いが明確に理解されていないケースも多く、採用や人材配置の場面で混乱を招くことがあります。「事務職で十分では?」「経理業務も事務の一部では?」といった誤解は、業務の属人化やミスのリスクを高める要因にもなります。この記事では、事務と経理の業務範囲や役割、求められるスキルの違いをわかりやすく整理し、適切な人材配置と採用判断につなげるための視点を解説します。
目次
事務と経理の違いとは?混同されがちな2つの職種を整理
「事務」と「経理」は、どちらも書類を扱うデスクワークが中心の業務であるため、混同されやすい職種です。しかし、実際の仕事内容や果たす役割には明確な違いがあります。適切に区別し、それぞれの職種に合った人材を配置することで、企業全体の生産性と業務の正確性が向上します。
主な違いを一覧で比較
| 項目 | 一般事務 | 経理 |
| 業務目的 | 各部署のサポート・業務補助 | 会社の財務状況を管理・記録する |
| 主な内容 | データ入力、電話対応、資料作成など | 仕訳、請求書処理、決算、税務対応など |
| 関係する部門 | 社内全体・来客・取引先 | 経営陣、税理士、金融機関 |
| 専門性 | 幅広く浅い | 会計・税務など専門知識が必要 |
このように、一般事務は「業務を支える幅広いサポート役」であり、経理は「企業の数字を扱う専門職」です。前者は部署横断的に働く傾向があり、後者は財務に直結する役割を担っています。
混同すると起こりやすい課題
- 経理経験のない事務スタッフに経理業務を兼任させることでミスが増加
- 業務の属人化により、担当者不在時に対応できる人がいない
- 専門性の必要な処理(決算・税務など)に対応しきれない
これらは、業務内容の理解不足や採用設計の曖昧さが原因で発生することが多いため、職種の線引きを明確にすることが非常に重要です。
結論:事務と経理は目的・業務内容・求められるスキルが異なる職種です。混同を避け、役割に応じた明確な区分と人材配置が企業運営の質を高めます。
一般事務の仕事内容|幅広い業務を支えるサポート役
一般事務は、社内の各部署を支える縁の下の力持ちとして、多岐にわたる業務を柔軟にこなす役割を担っています。日常的に発生する事務処理を円滑に進めることで、営業・人事・経理などの専門部署が本来の業務に集中できるよう支援するのが、一般事務の重要な役割です。
一般事務の主な業務内容
| 業務カテゴリ | 具体的な作業例 |
| 書類作成・管理 | 見積書・請求書・報告書・会議資料などの作成、ファイリング、印刷等 |
| データ入力 | 顧客情報や売上実績、社員データなどを専用ソフトやExcelに入力 |
| 電話・来客対応 | 社内外からの問い合わせ対応、来客応対、郵便物の仕分け・発送 |
| 備品管理・発注 | 文房具や社内設備の在庫管理、業者への発注手配 |
| 部署サポート業務 | 社員のスケジュール管理、会議室予約、社内イベント準備などの庶務全般 |
一般事務は、これらの作業を通じて社内の“潤滑油”として機能し、部署間の業務進行をスムーズに保つための基盤を提供しています。
専門性よりも“対応力と柔軟性”が求められる
一般事務には、会計や法務などの高度な専門知識は必須ではありませんが、その分「幅広い業務に対応できる汎用性」が強く求められます。日々の業務はルーチンに見えても、突発的な対応や状況の変化が起こる場面も多いため、臨機応変に動ける力が重視されます。
また、社内外のさまざまな人と接する機会があるため、ビジネスマナーやコミュニケーションスキルも業務遂行のうえで欠かせません。特に来客対応や電話応対は、企業の印象にも関わる重要な仕事です。
結論:一般事務は、特定の業務に特化せず幅広い業務を柔軟にサポートする職種です。正確さ・丁寧さ・コミュニケーション力を活かして、社内のスムーズな業務運営を支える存在です。
経理の仕事内容|企業の財務を管理する専門業務
経理は、会社の「お金の流れ」を正確に把握・記録・管理する専門職です。日々の取引から決算処理まで、数字を正しく扱うことで、企業が健全に経営できる環境を整えます。見た目は地味でも、経営判断や税務申告に直結する責任の重い業務を担っており、ミスが許されない分野でもあります。
経理業務の主な内容と流れ
| 業務区分 | 主な作業内容 |
| 日次業務 | 仕訳入力、伝票処理、領収書・請求書の確認、売上・支払データの管理 |
| 月次業務 | 試算表の作成、月次決算処理、各種帳簿の照合、科目別集計 |
| 年次業務 | 年次決算書の作成、法人税・消費税などの税務申告書対応、会計士・税理士との連携 |
| 予算・資金管理 | 年間予算の策定、資金繰り表の作成、経営層へのレポート |
| 税務対応 | 税制改正への対応、適正な税額計算、帳簿・証憑の保管とチェック |
これらの業務は、会計基準や税法に則って正しく処理される必要があり、専門知識と高い正確性が求められます。
経理は“経営を支える情報の番人”
経理が管理する数字は、会社の状態を把握するための「共通言語」とも言えます。現金や売掛金の状況、利益率、経費の推移などを通じて、経営層が適切な判断を下す材料を提供する役割も担っています。単なる入力作業ではなく、情報の信頼性を守る役割として、社内外からの信頼も厚いポジションです。
数字に強いだけでは務まらない職種
経理には、会計知識や数値感覚だけでなく、細部に目を向ける注意力・確認力・報連相を徹底する責任感が不可欠です。また、会計ソフトやExcelのスキル、他部署との調整力も実務を円滑に進めるうえで求められます。
結論:経理は、企業の財務状況を支える専門性の高い職種です。正確性と責任感を持ち、経営判断に貢献する“数字の専門家”としての役割を果たしています。
求められるスキルの違い|事務と経理で必要な能力とは
事務と経理は、どちらもデスクワーク中心の職種ですが、業務内容の性質が異なるため、求められるスキルにも明確な違いがあります。両者の役割を混同して採用や教育を進めてしまうと、業務の非効率やミスにつながりやすくなります。ここでは、一般事務と経理、それぞれに必要とされるスキルを具体的に比較しながら解説します。
スキル比較表|一般事務と経理の違い
| スキル分類 | 一般事務に求められる能力 | 経理に求められる能力 |
| 対応力・柔軟性 | 業務範囲が広く、突発的な依頼やマルチタスクにも対応できる力 | 優先順位を自ら判断し、計画的に処理を進める調整力 |
| コミュニケーション力 | 電話・来客対応、社内サポートとしての基本的なマナーや会話力 | 部署間や外部との調整、報告資料の説明などの対話力 |
| 事務処理能力 | 文書作成、資料整理、入力ミスのない正確な操作力 | 勘定科目の理解、会計ソフトの操作、数字の整合性を保つ力 |
| PCスキル | Word・Excelの基礎操作、ビジネスメール作成 | Excel関数(SUMIF、VLOOKUP等)や会計システムの操作能力 |
| 専門知識 | 特別な知識は不要(職場ごとのルールを覚えればOK) | 簿記、会計、税務、法令などの継続的な知識習得が必要 |
スキルの“深さ”と“汎用性”の違い
一般事務は、業務範囲が広く浅いため「汎用性」が重視されます。一方、経理は業務範囲が専門的で深いため、「専門性」と「正確性」が求められます。事務職では対応力と気配りが武器になりますが、経理職では数字への意識とルールの理解力が、実務の質を左右します。
採用・育成方針にも影響
採用においては、事務職ではポテンシャルや社内コミュニケーションへの適応力を重視し、経理職では簿記資格や実務経験を持つか、専門知識を学ぶ意欲があるかが大きな判断材料となります。
結論:事務と経理では、業務内容に応じて求められるスキルが大きく異なります。柔軟性と幅広さが強みの事務、専門性と正確性が求められる経理。それぞれの特性を理解し、適切な人材を配置することが業務効率とミス防止につながります。
経理業務の重要性|経営判断・資金管理との関係性
経理は、単なる「数字の処理係」ではありません。正確に集められた財務データは、企業が日々の活動を持続させ、将来の方針を決定するための根拠となる情報資産です。資金の流れを把握・管理し、適切な判断を下すためには、経理の果たす役割が極めて重要です。
経理業務が経営判断に与える影響
経営者や管理職が意思決定を行う際、主な根拠となるのが「財務データ」です。経理が作成する帳簿やレポートには、企業の健全性を示す多くの情報が含まれています。
| 項目 | 活用されるシーン |
| 試算表 | 月次の利益・損失を把握し、販管費の増減を分析する |
| 資金繰り表 | 今後の支払・入金予定を把握し、資金不足の予兆に備える |
| 損益計算書(P/L) | 利益率や固定費比率の見直し、事業の継続可否判断 |
| 貸借対照表(B/S) | 資産と負債のバランスを確認し、投資判断や銀行との交渉に活用 |
こうした資料が正確でなければ、経営判断に誤りが生じるリスクが高まります。つまり、経理が整備する数字の質が、そのまま会社の意思決定の質に直結するのです。
資金管理としての経理の責任
資金繰りの管理も経理の中心的な役割です。入出金のタイミング、固定費の負担、借入返済スケジュールなどを常に意識しなければなりません。資金が不足すれば、黒字倒産のリスクも高まります。
また、税金・社会保険料・取引先への支払いなど、期限厳守が求められる支出が多く存在します。これらを漏れなく処理するためには、経理による先回りの資金計画と綿密なスケジューリングが欠かせません。
経理が経営の信頼性を支えている
外部の関係者──たとえば金融機関、投資家、税理士、監査法人などに対しても、正確な会計処理と帳簿管理は企業の信頼性を左右します。ミスや不備があると、融資審査や税務調査で不利になるケースもあります。
結論:経理業務は、企業の数字を整えるだけでなく、経営判断と資金管理の根幹を支える戦略的な業務です。正確で透明な財務管理が、企業の安定経営と成長の基盤をつくります。
「経理もできる事務」では通用しない理由
採用や業務設計の現場で、「事務の延長で経理も担当してもらえば良い」「経理は事務スキルがあればできるだろう」といった認識が残っているケースがあります。しかし、実際には事務と経理は根本的に求められる専門性・責任の重みが異なり、「経理もできる事務」のままでは、正確で信頼性の高い経理体制を維持することは難しくなります。
経理は「誰でもできる仕事」ではない
経理業務には、日々の仕訳入力や請求処理だけでなく、以下のような法的・専門的な対応が含まれます。
| 項目 | 経理が担う役割 |
| 会計基準の理解 | 勘定科目の選定や決算処理に影響する知識 |
| 税法への対応 | 消費税・法人税・源泉徴収税などの申告業務 |
| 財務レポートの作成 | 月次・四半期・年次での経営数値の集計と分析 |
| 会計監査・税務調査対応 | 証憑の整備、帳簿の正確性担保、問い合わせへの対応 |
これらは単なるルールの暗記ではなく、背景にある「会計ロジック」や「税務リスクの回避」に関する深い理解が必要であり、汎用的な事務スキルでは対応が困難です。
両立によるリスクと業務圧迫
事務スタッフが経理業務を兼務すると、次のような問題が発生しやすくなります。
- 繁忙期にどちらの業務も中途半端になる
- 経理のチェック体制が不十分になり、ミスが見逃される
- 課題に気づいても専門知識がなく改善できない
- 突然の退職・異動で属人化が顕在化し、業務が停止する
このように、業務の質と安定性の両方が損なわれるリスクを抱えることになります。
経理は“専任体制”でこそ力を発揮する
経理業務は、毎月・毎年のスケジュールが決まっている「継続型のプロセス」です。そのため、専任者が責任を持って管理し、数字の整合性を常に保つことが求められます。加えて、法改正や税制変更など、継続的な知識アップデートも必要なため、専任でなければキャッチアップが難しい分野でもあります。
結論:「経理もできる事務」という考え方は、ミスの温床となり、企業の信用や経営判断に悪影響を与えかねません。経理は専門性の高い独立した職種として位置づけ、専任化を前提とした体制づくりが不可欠です。
適材適所の人材配置が企業の生産性を高めるカギ
企業における人材配置の基本は「適材適所」です。それぞれの職種や業務に求められるスキルや適性を理解したうえで、最も力を発揮できる場所に人を配置することが、業務の効率化・ミスの防止・社員の定着率向上に直結します。特に、事務と経理のように役割が似て見える職種ほど、細かい違いを見極めた配置が必要です。
不適切な配置が引き起こす業務課題
| 誤った配置例 | 発生しやすい問題 |
| 経理業務を未経験の事務担当に兼務させる | 処理ミスの頻発、税務対応の遅れ、チェック体制の不備 |
| 一般事務に専門性の高い人材を配置 | 能力を活かしきれず、やりがいの欠如や早期退職につながる可能性 |
| 業務内容を明確に区分しない | 属人化の進行、引き継ぎ困難、責任の所在が曖昧になることでのトラブル増加 |
こうした状況は、単に“人が足りないから”という理由で配置を急いだ結果生まれるケースが多く、組織の根本的な生産性を低下させてしまいます。
スキルと適性に応じた配置で業務効率がアップ
事務には柔軟性・対応力・広い視野が求められ、経理には正確性・専門知識・継続力が必要です。これらの違いをしっかりと把握し、職種ごとの本質に合った人材を配置することが、パフォーマンス最大化の鍵となります。
また、適性に合った仕事を任せられた社員は、モチベーションが上がり、自らスキルを磨こうとする傾向があります。結果として、職場の雰囲気や人間関係も良好になり、組織全体の活性化にもつながる好循環が生まれます。
中長期的視点での配置と育成が重要
人材配置は短期的な穴埋めではなく、中長期的な体制づくりの一環として行うことが理想です。事務から経理へ段階的に育成したい場合も、明確な計画と教育支援を設けることで、無理なくスキル移行が可能になります。外部リソースの活用や業務の一部委託なども併用し、無理のない体制構築を行うべきです。
結論:業務内容と人材の適性を正しく把握し、適材適所の配置を行うことが、企業全体の生産性と業務の質を向上させます。属人化を避けた戦略的な人材設計こそが、持続可能な組織運営の土台となります。
結論|業務の違いを理解し、経理人材を戦略的に採用しよう
企業の成長を支えるうえで、事務と経理はどちらも欠かせない存在です。しかし、それぞれの役割や必要とされるスキル、責任の重みには大きな違いがあります。「どちらもバックオフィス業務だから似ている」という曖昧な認識のままでは、適切な人材配置や採用ができず、業務効率や信頼性を損なう結果になりかねません。
業務内容を理解することが最初の一歩
本記事で解説した通り、一般事務は「社内全体の業務を支えるサポート役」、経理は「企業の財務を正確に管理する専門職」です。この違いを採用や育成の段階から意識することで、それぞれの業務に合った人材を見極め、無理のない配置が可能になります。
| 項目 | 一般事務 | 経理 |
| 業務範囲 | 幅広く柔軟なサポート業務 | 財務・税務など専門的かつ正確性重視の業務 |
| 求められる適性 | 対応力・気配り・コミュニケーション力 | 数字感覚・慎重さ・責任感・論理的思考力 |
| 配置の考え方 | 幅広い業務に対応できる人を柔軟に配置 | 継続性・専門性を重視して専任化が理想 |
経理人材は“戦略的”に採用すべき存在
経理業務は、企業の資金繰りや税務リスク、経営判断に直結します。そのため、一時的な穴埋めではなく、中長期で活躍できる戦力としての採用・育成が必要です。経理の基礎知識を持つ人材はもちろん、会計や税務に強い外部パートナーの活用も視野に入れ、体制を強化することが求められます。
正しい区別が組織の生産性を底上げする
業務の性質や役割の違いを理解せずに人を配置すると、処理ミスや退職リスクが高まり、結果として組織全体のコストが増える可能性があります。逆に、それぞれの仕事にふさわしい人材を適切に配置できれば、パフォーマンスが安定し、社員のやりがいにもつながります。
結論:事務と経理の違いを正しく理解することが、企業全体の業務品質と経営安定を支える第一歩です。特に経理人材は、戦略的視点での採用・配置によって、経営を支える中核としての力を発揮します。
経理人材の確保や育成にお悩みなら、経理代行の活用をご検討ください
事務と経理は明確に役割が異なり、特に経理は専門性・正確性・責任感が求められる重要なポジションです。しかし、「適性のある人材が採用できない」「育成する余裕がない」「属人化が不安」といった課題を感じている企業様も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、経理代行サービスの導入をぜひご検討ください。
- 経験豊富な専門スタッフが仕訳・請求処理・月次決算・税務対応まで幅広くサポート
- 人材の確保や育成にかかるコスト・時間・リスクを大幅に削減
- 経理業務の標準化・効率化・可視化を実現
- 社内の人材は本来の業務や経営課題に集中できる体制づくりが可能に
当社では、企業の状況に合わせた柔軟なプランをご用意しています。経理部門の課題解決に向けて、最初の一歩として無料相談をお試しください。
📩 まずは無料相談から、お気軽にお問い合わせください